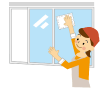
みなさんは12月13日は何の日かご存知でしょうか?
江戸時代、正月を迎える準備を始める日のことを「正月事始の日」「正月始め」としていました。
正月を迎えるにあたり、大掃除することを「煤払い」と言い、
12月13日を煤払いの日として定めていたようです。
「煤払い」はお正月の歳神様(新しい年の五穀の豊作を約束してくれる神様)をお迎えする神事で、
1年分の汚れを落とし、屋内外の掃除をし神棚を祓い清め正月の準備を始める年末の行事をいいます。
今でも多くの寺社で(地方で日にちは異なりますが)煤払いが行われているようですが、
現代の一般家庭では宗教的な意味合いは失われつつあり、暮れの大掃除と言う形になっています。
煤払いの日は旧暦では鬼宿と言い、大変縁起が良い日だと言われています。
毎年、暮れに慌てて大掃除をしていましたが、今年は早めに新年の準備を始めてみようかと思います。
(AK)
|