|
|
 |
|
[035]
「なぜサイコロの1の目は赤い?」
2006/8/25
|
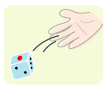 大正期まではサイコロの目はすべて黒かったようです。ではいつから赤くなったのか。
大正期まではサイコロの目はすべて黒かったようです。ではいつから赤くなったのか。
それには諸説があり、1926年に和歌山のサイコロ業者が日の丸をモチーフに1の目だけを赤色にして発売したところ、
大当たりしたので、それ以来日本では1の目が赤いサイコロが一般的になったという説。
サイコロの目は方角を示し、1は『天』、6は『地』、そして2は『西』、3は『北』、4は『南』、5は『東』を指しているので、『天』を指す1は太陽をイメージして赤くなったという説。
大正から昭和にかけてすごろくが流行し、女性や子供がサイコロで遊ぶようになり、関西の会社がゲーム用に
1の目が赤いサイコロを作ったという説。この説が一番最もらしい気がしますが実際のところはどうなのでしょうか。
ちなみに1の目が赤いのは世界でも日本だけです。(OR)
|
|
[034]
「蚊に刺されやすい人」
2006/8/10
|
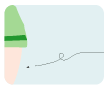 夏の天敵「蚊」。蚊に刺されるさされやすさ。O型の人、お酒をよく飲む人などが刺されやすいとか。
夏の天敵「蚊」。蚊に刺されるさされやすさ。O型の人、お酒をよく飲む人などが刺されやすいとか。
O型の人が刺されやすい原因は、O型の人の赤血球の表面を覆っている物質にあるようです。
蚊は通常、花の蜜や果汁、樹液などをエサとしているのですが、メスの蚊は産卵期になるとタンパク質が必要なため、
人の皮膚を刺し血を吸うようになります。O型の人の血液型の表面を覆う物質は、花の蜜と非常に似ているので、蚊は花の密と間違えてO型の人に近づいてくるそうです。
お酒をよく飲む人が刺されやすいというのは、二酸化炭素と関係があります。
蚊は、私たちの呼吸により吐き出される二酸化炭素を感知して寄ってきます。「二酸化炭素を吐き出す=ほ乳類」ということを蚊は知っているのです。
お酒を飲むと、アルコールの分解の途中で二酸化炭素を吐き出す量が増え、呼吸数も増えます。そのため蚊に見つけられやすくなる=刺されやすくなるのです。
(OR)
|
|
[033]
「ものさし(定規)の溝」
2006/7/31
|
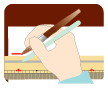 小学校で使った竹の定規、皆さん覚えていますか?目盛りと反対の側に溝が掘ってあったと思います。最近のアクリル製定規にもこの溝がついているものがあります。
この溝、何に使うかご存知ですか? 飾り? それとも滑り止め?
小学校で使った竹の定規、皆さん覚えていますか?目盛りと反対の側に溝が掘ってあったと思います。最近のアクリル製定規にもこの溝がついているものがあります。
この溝、何に使うかご存知ですか? 飾り? それとも滑り止め?
実はこれ、筆で直線を引くためのものなのです。「ガラス棒」という両側が丸くなっている棒を筆といっしょに箸のように持ち、棒を溝に滑らせて直線を引きます。
この技法を「溝引き」といいます。
この夏休み、宿題のポスターなどを描くとき、活用されてはいかがでしょうか。
「すごい!」と、子供に言われるかも…。
●「ガラス棒」でなく割り箸等でも代用はできます。先を丸く削ったりして、溝との接点がブレないようにしてください。簡単にできますが何度か練習してからやってください。
筆の力加減、絵の具の濃さなど、少しコツが必要です。 (AM)
|
|
[032]
「土用の丑」
2006/7/14
|
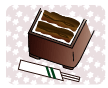 土用の丑は7月20日頃になります。この丑の日には「うの字」のつくものを食べる習慣があるようです。
ご存知のとおりうなぎ・梅干・うり・などの夏の疲れをとり夏バテ防止になる食べ物です。
土用の丑は7月20日頃になります。この丑の日には「うの字」のつくものを食べる習慣があるようです。
ご存知のとおりうなぎ・梅干・うり・などの夏の疲れをとり夏バテ防止になる食べ物です。
先日ひつまぶしを食べました。ひつまぶしとはうなぎの蒲焼を1cmぐらいに短冊に刻んでおひつの中に入っているご飯の上にまぶして食べる名古屋の名物料理です。
食べ方は1杯目はそのまま食べます。2杯目は薬味とわさびを適当にかけ食べます。3杯目は薬味・わさび・のりを好みにあわせて入れお茶漬けにして食べます。
関西人なので基本的にはたれがたっぷりかかった鰻丼が好きなので最初うなぎをお茶漬けのように食べるなんて…と思いましたがわさびと山椒の実がうなぎとよくあい、
とてもおいしかったです。(UM)
|
|
[031]
「カレー」
2006/6/23
|
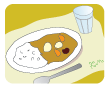 日本ではカレーのルウが市販されていて、既に数種類のスパイスがブレンドされているのでカレールウだけで
おいしいカレーが簡単に作れます。一方インドではカレールウやカレー粉というのは存在せず、何種類ものスパイスをあわせて作るのがカレー料理のようです。
日本ではカレーのルウが市販されていて、既に数種類のスパイスがブレンドされているのでカレールウだけで
おいしいカレーが簡単に作れます。一方インドではカレールウやカレー粉というのは存在せず、何種類ものスパイスをあわせて作るのがカレー料理のようです。
このスパイス・・・カレー独特の風味や香りで食欲を増す働きがありますがそれだけではないようです。唐辛子にはカプサイシン・こしょうにはピペリン
という成分があり脂肪の分解を促進します。にんにくには疲労回復作用があり、又しょうがには発汗作用を促し新陳代謝をよくする働きがあるので肥満予防にも効果的です。
カレーを食べて体が熱くなるのはこれらのスパイスの働きによって血液の循環が良くなっている証拠なのです。(UM)
|
|