|
|
 |
|
[015]
「秋の花、金木犀」
2005/10/14
|
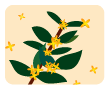 金木犀が匂ってくると秋だなぁと感じるのは私だけでしょうか??どこか懐かしくそれでいて甘く切ない香り。秋を代表する花ですよね。
金木犀が匂ってくると秋だなぁと感じるのは私だけでしょうか??どこか懐かしくそれでいて甘く切ない香り。秋を代表する花ですよね。
この金木犀、中国南部の桂林地方原産で日本へは江戸時代初期に渡来。開花時期は9月後半から10月初旬まで
。雌雄異株で日本には雄株しか渡来していないので果実は見られず、常緑小高木で幹は太く高さは3から5mにもなります。葉は対生し楕円形。秋には甘くて強い芳香を放つ橙黄色の小さな花が咲きます。花冠は4裂し、雄花には雄しべ2個と先の尖った不完全な雌しべが1個あります。ほとんどの花弁が色を残したまま落下し、咲いた後で雨風があると儚く散ってしまいます。花言葉は気高い人、謙遜、初恋。甘く強い香りでそばを通
る人の‘気を引く’ところからだそうで、人を魅了して止まないのも納得ですよね。(UK)
|
|
[014]
「目には目を、歯には歯を」
2005/10/11
|
|
「やられたらやり返す」の意味として誤ってよく使われる「目には目を 歯には歯を」。
これは、紀元前18世紀のバビロン王ハムラビが制定した「ハムラビ法典」の中の「同害復讐法」に出てくるものです。
本来の意味は「目を害されたら、目を害して良い」ではありません。「目を害された時、腹が立って目だけでは許せぬ!やられた以上に、何なら命まで奪ってしまえ!」と言う事になりかねないので、「自分が害された以上に害してはいけない。相応の罪で相手を許しなさい。」という法律なのです。
また、その後の旧約聖書でも使われていますが、その中では「目に危害を加えた者は、その(自らの)目によって報復を受けなければならない。」とされています。(IM)
|
|
[013]
「地震、雷、火事、おやじ」
2005/9/22
|
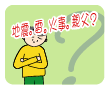 昔からこわいもののたとえで、よく言ったものです。 でも、「おやじ」って変ですよね。災害の後に人?
確かに厳しくて怖い父親はいますが…。 子供のころは本当に「親父」のことだと思っていました。もしかすると、今でもそう思っている人もいると思います。
ところが実はこの「おやじ」、「大山嵐(おおやまじ)」がなまったもので
「大山嵐」の漢字からも想像できますが、台風のことなんです。「タイフーン」を「台風」と翻訳する前は「大山嵐」や「野分(のわき)」と呼んでいたそうです。「親父」として定着するほど昔は父親は怖かったというこということでしょうか。
昔からこわいもののたとえで、よく言ったものです。 でも、「おやじ」って変ですよね。災害の後に人?
確かに厳しくて怖い父親はいますが…。 子供のころは本当に「親父」のことだと思っていました。もしかすると、今でもそう思っている人もいると思います。
ところが実はこの「おやじ」、「大山嵐(おおやまじ)」がなまったもので
「大山嵐」の漢字からも想像できますが、台風のことなんです。「タイフーン」を「台風」と翻訳する前は「大山嵐」や「野分(のわき)」と呼んでいたそうです。「親父」として定着するほど昔は父親は怖かったというこということでしょうか。
…でも最近「親父」の威厳って? これを知ったからといって災害がなくなるわけでも対策ができたわけでもありませんが…
「備えあれば憂い無し」 前もって災害対策しておきましょう。(AM)
|
|
[012]
「アンカーの意味」
2005/9/16
|
 運動会・体育祭の季節になりましたね。そこでリレーで最後に走る人をアンカーといいますが、何故アンカーと呼ばれるのでしょう?アンカーとは本来、船をとめる為に使う錨(イカリ;anchor)のことです。ここから綱引きで最後尾に体重の重い人を置き、綱を繋ぎ止める様子が錨に例えられアンカーと呼ばれ、更にそれが転じて最後に走る人のことをアンカーと呼ぶようになったといわれています。(OG)
運動会・体育祭の季節になりましたね。そこでリレーで最後に走る人をアンカーといいますが、何故アンカーと呼ばれるのでしょう?アンカーとは本来、船をとめる為に使う錨(イカリ;anchor)のことです。ここから綱引きで最後尾に体重の重い人を置き、綱を繋ぎ止める様子が錨に例えられアンカーと呼ばれ、更にそれが転じて最後に走る人のことをアンカーと呼ぶようになったといわれています。(OG)
|
|
[011]
「シーザーとカレンダー」
2005/9/9
|
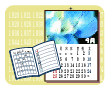 9月の声を聞くと文具店、書店などの店頭に多種多彩な来年のカレンダーやスケジュール帳やらが並びだし、
もうそんな時期がきたんだなと惰性で過ごした今日までを振り返ったり、来年こそは!と決意を新たにしていそいそと購入したりしてしまいます。
9月の声を聞くと文具店、書店などの店頭に多種多彩な来年のカレンダーやスケジュール帳やらが並びだし、
もうそんな時期がきたんだなと惰性で過ごした今日までを振り返ったり、来年こそは!と決意を新たにしていそいそと購入したりしてしまいます。
そこでカレンダーの起源について調べてみると、2000年前に作られた“ユリウスの暦”の影響を受けているそうで、このユリウスというのが、かの『賽は投げられた』『ブルータスお前もか?』などの名文句で有名なローマ帝国終身独裁官ユリウス・カエサル(アメリカの読みでジュリアス・シーザー)で、天文学者に命じて作らせたそうです。シーザーは7月生まれで、7月はシーザーの名前Julius(July)にちなんだ名称とのこと。(AS)
※暦についてのサイトをリンクのページにのせましたので、もっと知りたい方はご覧下さい。
|
|