|
|
 |
|
[030]
「父の日」
2006/6/30
|
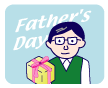 6月の第3日曜は父の日です。5月の母の日はほとんどの人に知られていて日頃の感謝を込めてプレゼントをする人が
多いと思います。しかし父の日はどうでしょうか?何もしない・又いつだったか忘れている人も多いのではないでしょうか?
6月の第3日曜は父の日です。5月の母の日はほとんどの人に知られていて日頃の感謝を込めてプレゼントをする人が
多いと思います。しかし父の日はどうでしょうか?何もしない・又いつだったか忘れている人も多いのではないでしょうか?
父の日はアメリカが発祥地とされていて、
ある夫人が父の日がないと不公平だという事で亡き父のお墓の前に白いバラを捧げた事が始まりとされている説があるようです。母の日はカーネーションですが
父の日の花はバラだそうです。
皆さんは何かされますか?(UM)
|
|
[029]
「食中毒」
2006/6/2
|
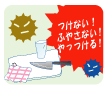 食中毒は年中発生しますが、特に6月から9月の間は気温が高く、
他の季節に比べて微生物の生育が早いため食中毒が発生しやすくなります。
原因には食器やまな板、ふきん等の調理器具が清潔に保たれていないことや、冷蔵庫に物を詰め込みすぎたり、
ドアを頻繁に開け閉めしたりする事で庫内の温度調節が十分に行われない事が挙げられ、その結果、菌が増殖してしまいます。
食中毒は年中発生しますが、特に6月から9月の間は気温が高く、
他の季節に比べて微生物の生育が早いため食中毒が発生しやすくなります。
原因には食器やまな板、ふきん等の調理器具が清潔に保たれていないことや、冷蔵庫に物を詰め込みすぎたり、
ドアを頻繁に開け閉めしたりする事で庫内の温度調節が十分に行われない事が挙げられ、その結果、菌が増殖してしまいます。
予防のポイントは、細菌を「つけない、ふやさない、やっつける」です。手や調理器具はこまめに洗う。買い物から帰ってきたらすぐに 冷蔵庫に入れる。
作り置きのものなどは食べるときに充分加熱する。このようなことに気をつけ食中毒を予防しましょう。(OR)
|
|
[028]
「親知らず」
2006/5/19
|
 親知らず以外の永久歯はだいたい12才頃までに生え揃いますが、親知らずは20才前後、40才を過ぎてから生えてきたりします。
なぜそのような歯が生えてくるか...。大昔は、生のまま食べたり固い木の実を食べるのに丈夫な顎と歯が必要でしたが、
火を使い食べ物を調理するようになっていくに従い顎が退化していき、親知らずが生えるスペースがなくなっていったからです。
親知らず以外の永久歯はだいたい12才頃までに生え揃いますが、親知らずは20才前後、40才を過ぎてから生えてきたりします。
なぜそのような歯が生えてくるか...。大昔は、生のまま食べたり固い木の実を食べるのに丈夫な顎と歯が必要でしたが、
火を使い食べ物を調理するようになっていくに従い顎が退化していき、親知らずが生えるスペースがなくなっていったからです。
そのため歯が横向きなどで生えてきて歯茎や顎の骨を圧迫して痛くなったりします。
また名前の由来は二つあり、ひとつは、生えてくる時期が20歳前後と、親から独立する年頃なので、親が知らないうちに生えてくるから。
もうひとつは、昔は平均寿命が短かったので、親知らずが生えてくる頃にはもう親は亡くなっていることが多く、
親を知らずに生えてくるからというものです。(OR)
|
|
[027]
「こどもの日の由来」
2006/4/26
|
 起源は古代中国時代です。 端午の端は「最初」、午は「うま」という事で、「五月の最初の午の日」に行われる節句という意味をもちます。
起源は古代中国時代です。 端午の端は「最初」、午は「うま」という事で、「五月の最初の午の日」に行われる節句という意味をもちます。
当初、こどもの日は5月5日ではありませんでした。 午と五のゴロ合わせで、5月5日となり、大切な厄払いの日と考えられるようになりました。
鯉のぼりを飾ることが広まったのもこの頃で、武士の家に男の子が生まれると、出世するようにとの願いを込めて、鯉のぼりを門前に立て、一般
にその風習が伝わりました。また、庶民にはのぼりを立てることは許されませんでした。日本の祝日とされたのは、戦後(1948年頃)のことで、それまでは、男子のみの祝いでした。
後に、男女共の祝い日として、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日と定義づけました。
http://www13.ocn.ne.jp/~mh910/kodomonohi.htmより引用しました。(IY)
|
|
[026]
「桜餅」
2006/4/7
|
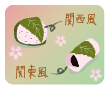 桜の葉や花を食べることができるのは、ご存知の通りです。
桜の葉や花を食べることができるのは、ご存知の通りです。
桜の葉は、桜餅などの和菓子や料理などに使われます。食用となるのはオオシマザクラの若葉で約80%は伊豆地方で生産されています。
桜餅は関西風と関東風では由来も形も違います。 水で戻した道明寺粉(もち米を一度蒸して乾燥させたものを粗く砕いたもの)を蒸して餡を包み、
塩漬けにした桜の葉を巻くのが関西風桜餅(道明寺桜餅)。
溶いた小麦粉を焼いて皮で餡を包み、外側を塩漬けにした桜の葉で覆うのが関東風桜餅(長命寺桜餅)。
関東風桜餅は食べたことがないですが、道明寺のようにもち米の感触がないのは関西人の私には物足りないような気がします。(OR)
|
|