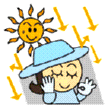
梅雨が終わるといよいよ夏です。
海に山にとアウトドアにはもってこいの季節ですが一つ気になる事が・・・それは日焼けです。
どちらかというと色が白い方なので、短時間でも日焼け止めを塗らずに外出すると
すぐに黒くなってしまいます。
紫外線にはUVA,UVB,UVCの3種類ありますが、
UVCはオゾン層のおかげで地表には届きません。
UVAは生活の中で浴びる紫外線で肌の奥まで届くものです。
UVBは屋外において浴びる紫外線で、長時間浴びると一時的に赤く炎症を起したりします。
よく日焼け止めにはPAやSPFという表示がされていますが
PAとはUVAをどのくらい防止出来るか、
SPFとはUVBをどのくらい防止出来るかという目安になっています。
3段階に区分され+の値が高い程効果が高いといわれています。
日常生活においてはSPF10前後で十分ですが外で軽くスポーツをする時には
SPF30、リゾート地に行く時には
SPF50位あるものを使うといいそうです。
今は美容液や乳液にSPFが含まれるものが多く出ているので
そういうものと日焼け止めを一緒に使うとより効果的かもしれませんね。(UK)
|