|
|
 |
|
[045]
「高野豆腐」
2007/1/12 |
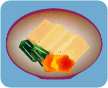 鍋に入れたり、温かいお豆腐が美味しい季節になってきました。
今回は、その豆腐の加工品の高野豆腐について調べてみました。
高野豆腐は、関西では、煮物・巻寿司等にいれたりする親しみやすい食べ物ですが、その製法が豆腐を凍らせて乾燥させてものだとはあまり知られていません。
高野豆腐という名前の由来は、高野山の冬の厳しい寒さで、豆腐が凍ってしまいそれを食べてみたところ、美味しいという事になり、その後高野山を中心に関西で普及していったためという説があります。
関西では、高野豆腐の名前で親しまれていますが、他に、凍り豆腐・ちはや豆腐・凍み豆腐・連豆腐・一夜凍りと地方によっていろいろな呼び方がある様です。
高野豆腐は、ダイオキシンの排出・コレステロールの抑制作用・骨粗鬆症の予防などダイエット食品としても最適です。(IT)
鍋に入れたり、温かいお豆腐が美味しい季節になってきました。
今回は、その豆腐の加工品の高野豆腐について調べてみました。
高野豆腐は、関西では、煮物・巻寿司等にいれたりする親しみやすい食べ物ですが、その製法が豆腐を凍らせて乾燥させてものだとはあまり知られていません。
高野豆腐という名前の由来は、高野山の冬の厳しい寒さで、豆腐が凍ってしまいそれを食べてみたところ、美味しいという事になり、その後高野山を中心に関西で普及していったためという説があります。
関西では、高野豆腐の名前で親しまれていますが、他に、凍り豆腐・ちはや豆腐・凍み豆腐・連豆腐・一夜凍りと地方によっていろいろな呼び方がある様です。
高野豆腐は、ダイオキシンの排出・コレステロールの抑制作用・骨粗鬆症の予防などダイエット食品としても最適です。(IT) |
|
[044]
「七草がゆ」
2007/1/5 |
 皆様は、七草粥の七草の名前をちゃんと挙げる事ができますか?
答えは、芹(セリ)、薺(ナズナ)、御形(ゴギョウ)、繁婁(ハコベ・ハコベラ)、菘(スズナ)、蘿蔔(スズシロ)、仏座(ホトケノザ)です。
お正月の七日の朝、七草を入れた粥を食べて邪気を払い、無病息災を願います。またごちそうで弱った胃を休め緑黄色野菜の少ない冬場に必要な栄養を摂取できる、古くは平安時代から伝わる風習だそうです。
七草には、それぞれに効能があるため、七草粥を食べる事によって、リウマチ・神経痛・増血作用・利尿作用・咳.痰に良い・整腸効果・消化促進・高血圧予防などといった効果を一度に得る事ができます。(IT)
皆様は、七草粥の七草の名前をちゃんと挙げる事ができますか?
答えは、芹(セリ)、薺(ナズナ)、御形(ゴギョウ)、繁婁(ハコベ・ハコベラ)、菘(スズナ)、蘿蔔(スズシロ)、仏座(ホトケノザ)です。
お正月の七日の朝、七草を入れた粥を食べて邪気を払い、無病息災を願います。またごちそうで弱った胃を休め緑黄色野菜の少ない冬場に必要な栄養を摂取できる、古くは平安時代から伝わる風習だそうです。
七草には、それぞれに効能があるため、七草粥を食べる事によって、リウマチ・神経痛・増血作用・利尿作用・咳.痰に良い・整腸効果・消化促進・高血圧予防などといった効果を一度に得る事ができます。(IT) |
|
[043]
「ゆず湯」
2006/12/15 |
 江戸時代、冬至の日(1年で一番昼が短く、夜が長い日)に、お湯で沐浴したのがゆず湯のはじまりだとされ、ゆず湯に入れば風邪をひかないといわれています。
江戸時代、冬至の日(1年で一番昼が短く、夜が長い日)に、お湯で沐浴したのがゆず湯のはじまりだとされ、ゆず湯に入れば風邪をひかないといわれています。
また、冬至(とうじ)を湯治(とうじ)、柚子(ゆず)を融通(ゆうずう)がきくようにとの願いがかけられているそうです。
ゆずには、ビタミンCがたっぷりで、皮にはペクチンや精油成分、種にはアミグダリンなどの成分が含まれており、新陳代謝・美白効果・保湿・殺菌効果があるとされています。
加えて、冬至の日にかぼちゃを食べると中気にならないといわれています。(IT )※中気…脳卒中
|
|
[042]
「海老の身」
2006/12/1 |
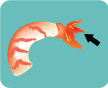 学生時代にお寿司屋さんでアルバイトをしていた時、私が出勤して最初にする作業は、えびの殻剥き。板前さんが出汁でたいて、下ごしらえしてある小海老の殻を剥くのです。
その時、私は初めて知ったのですが、
みなさんは、尻尾の中にも身があるのをご存じでしたか?
真ん中の小さい尻尾の殻をパキッと折って剥くと実はその中にもちょっぴり身があるのです。
小海老の尻尾の殻はどうなっているか、料理人の手間がかけられているかチェックしてみて下さい。(IT)
学生時代にお寿司屋さんでアルバイトをしていた時、私が出勤して最初にする作業は、えびの殻剥き。板前さんが出汁でたいて、下ごしらえしてある小海老の殻を剥くのです。
その時、私は初めて知ったのですが、
みなさんは、尻尾の中にも身があるのをご存じでしたか?
真ん中の小さい尻尾の殻をパキッと折って剥くと実はその中にもちょっぴり身があるのです。
小海老の尻尾の殻はどうなっているか、料理人の手間がかけられているかチェックしてみて下さい。(IT)
|
|
[041]
「シュークリームは靴磨きクリーム??」
2006/11/17 |
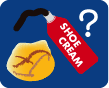 ケーキ屋さんやスーパーなどあちらこちらで売られているお菓子の定番「シュークリーム」
ケーキ屋さんやスーパーなどあちらこちらで売られているお菓子の定番「シュークリーム」
この語源はフランス語 『chou a la creme シュ・ア・ラ・クレーム』からきたもので、
『シュ』とはキャベツのことで、ふっくらとした焼き上がりがキャベツのように見えることから
名づけられました。また『クレーム』は英語読みのクリームが当てられたようです。
英語と思い使うと『shoe cream』 靴磨き用クリームとなってしまうかもしれませんね。
ちなみに英語では『cream puff クリームパフ』というようです。(OG)
|
|